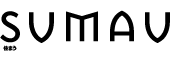デザインインフォメーション
[丸の内スペシャル]
苦悩のなかで自分自身を描き続けた画家
『没後30年 鴨居玲展 踊り候え』

1960年代から80年代にかけて活躍した鴨居玲。没後30周年を記念した回顧展『没後30年 鴨居玲展 踊り候え』が東京ステーションギャラリーで開催されている。国内外各地で出会った社会の底辺で生きる人々をモティーフにした作品は、そのいずれもが自身を投影した自画像ともいわれている。油彩、水彩、デッサン、遺品など約100点を展示した回顧展。東京では25年ぶりの開催となる。7月20日までの開催。

《静止した刻》1968年 東京国立近代美術館所蔵
世界各地で出会った、底辺を生きる人たちの
「それでも生きる」という力強さ
鴨居玲は、人間を多く描いた画家だ。鴨居本人も「わたしが興味があったのはただ人間だけだ」と語っていたという。
画家人生の前半は、さまざまな表現を模索した。シュルレアリスム、抽象などを経て、人物へと移行していく。
南米、パリ、ローマ、そしてスペイン各地を放浪しながら、行く先々で出会った人々を描いた作品には、「生きること」に対峙した人の姿が見事に表現されている。しかしそれはけっして生きる喜びや明るい未来を感じさせるものではない。
虚空を見つめているような老婆の姿。腕を失った左の袖を縛り地べたに座る廃兵の丸まった背中。酩酊しバランスを崩しそうになった老夫。
世界各地で社会の底辺を生きる人々をモティーフに描き続けた作品からは、「つらいこと、苦しいことばかりだけれど、それでも生きる」、そんな強い意志が感じられる。同時に、死ぬまで生き続けねばならないという「業(ごう)」にも近い生きることの生々しさを見せつけられた。

《おっかさん》1973年 個人蔵

《教会》1976年 ひろしま美術館所蔵

《石の花》1980年 個人蔵
不安、孤独、迷い、焦燥、絶望、諦め……
込められた「描くこと」への想い
1977年に帰国した鴨居は、神戸にアトリエを構え創作活動を続けた。そこで待ち受けていたのは、画家としての飛躍ではなく表現者としての苦しみだ。裸婦や恋人たちなど新しい画題に取り組んだものの、展開が広がるには至らない。
創作に行き詰った鴨居が突き詰めていったのは自画像だ。鏡に映る自らの姿をカンバスに写し取りながら、内に渦巻くさまざまな感情を絵筆に乗せた。
生気がなく、疲れ切った男。半ば口を開き、目はほとんど閉じられている。力なく肩を落として佇む姿は、諦めの境地にいるようにも見える。
描けないことへの不安や孤独感、迷い、焦燥感、絶望、そして諦め。カンバスの男は、痛ましいほどのリアリティを持って悲哀と苦悩を訴えかけてくる。
1985年9月7日。鴨居は57歳で自らの生に終止符を打つ。顔立ちは端整で身長180cm近い体格だったが、最後まで自信に満ちた堂々とした姿が描かれることはなかった。
なぜ、そこまで苦悩しても描き続けなければならなかったのか。苦しみながら、それでも筆を走らせ続けることで、鴨居は少しでも救われたのだろうか。
展示の最後のセクションには、デッサンが並んでいた。鴨居はデッサンを重視した画家だ。1枚の絵を描くために100枚ものデッサンを描くことも少なくなかったという。
素描の幾重にも重なった線は、伸びやかで生き生きとしている。表現すること、描くことへの純粋な想いが凝縮されているように見えた。
(文・久保加緒里)

《ミスターXの来た日 1982.2.17》1982年 個人蔵

《出を待つ(道化師)》1984年 個人蔵

《勲章》1985年 笠間日動美術館所蔵

《蛾》1976年 個人蔵
鴨居 玲(かもい れい)1928 – 1985年
石川県金沢市生まれの洋画家。1946年、金沢美術工芸専門学校に入学、宮本三郎に師事。1965年、南米、パリ、ローマを旅する。1967年、二紀会同人に再び推挙。1968年、初の個展。この時、下着デザイナーの姉・鴨居羊子を通じて知り合った小説家・司馬遼太郎と親交をもつ。1969年、昭和会賞と安井賞を受賞。1971年、スペインのラ・マンチャ地方にあるバルデペーニャスにアトリエを構え、制作に没頭(~74年)。 1985年、没。享年57歳。
北陸新幹線開業記念
没後30年 鴨居玲展 踊り候え
会場:東京ステーションギャラリー
住所:東京都千代田区丸の内1−9−1
会期:2015年5月30日(土)~2015年7月20日(月・祝)
開館時間:10:00~18:00(金曜日は~20:00、入館は閉館30分前まで)
休館日:月曜日(7月20日は開館)
入館料:一般900円、高校・大学生700円、中学生以下無料
※20名以上の団体は100円引
※障がい者手帳等を持参の方は100円引、その介添者1名は無料
問い合わせ:03-3212-2485