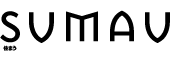パリとアート
美術館では見られない画家の素顔。
芸術と生活に全てを捧げた藤田嗣治、最後の家。

パリから電車とバスを乗り継いで約1時間。エソンヌ県の小さな村ヴィリエ・ル・バクルは、パリをちょっとだけ離れた郊外とは思えない自然豊かな風景が広がる。初夏ともなれば鮮やかな新緑が太陽の光に輝き、鳥たちはさえずり、美しい季節を謳歌する。

ヴィリエ=ル=バークルの遊歩道
ここには、第一次世界大戦直前の1913年にフランスに渡り、エコール・ド・パリの画家として知られた「FOUJITA(フジタ)」こと藤田嗣治の最後の住居兼アトリエが残されている。
藤田嗣治といえば、ご存じの通り1920年代のパリ「狂乱の時代」にピカソやコクトーなどとともに一世を風靡した画家の一人だ。当時もっとも賑やかな繁華街だったモンパルナスを中心に生活し、その後、一時日本に帰国し、従軍画家として日本軍の凄惨な戦地を目の当たりに。戦後は日本を追われるようにフランスに戻ってきて帰化し、この国に骨を埋めようと決めたのだった。激動の時代を乗り越えた彼が、人生最後の日々をこんな穏やかな地で過ごしたいと思ったのは、もしかしたら自然ななりゆきだったのかもしれない。
ここに彼と君代夫人が移ってきたのは1961年のこと。すでにフランス国籍を取得し、59年にはシャンパーニュの街・ランスのノートルダム大聖堂でカトリックの洗礼も受けていた。藤田の本やカタログなどを手がけた編集者のピエール・ド・タルタがこの地方で水車小屋を改造したアートセンターをオープン。また晩年の藤田夫妻ともっとも親しかった日本人画家の田淵安一がこの近くに住居を構えていて、彼らを訪れた道すがら、藤田は古くさびれたこの家を見つけ、直感に導かれるように1960年10月4日これを購入する。74歳になっていた彼だったが、なんとそこから約1年をかけて自分好みに家を改装していったという。

街路とは反対の庭側から見た家は3階建 ©Maison-atelier Foujita. CD91. Fondation Foujita. ADAGP2019
この「メゾン・アトリエ・フジタ(藤田嗣治の住居兼アトリエ)」は現在、一般に公開されていて、ガイド付きで彼らが暮らした家を見学することができる。
まるで昨日までそこにいたかのように。
庭に面した1階には台所。50-60年代に流行した「フォーマイカ」のキッチンセットの上には、夫妻が使った調理器具や容器がそのまま残っている。今ならアンティークショップにありそうなヨーロッパのキッチンウェアに混じって、日本の炊飯器やレトロな昭和のかき氷機「アイスペット」まであって、まるで二人がいまここにいても不思議はないような雰囲気がある。

1階の台所:当時フランスでも人気があったフォーマイカのキッチンキャビネット ©Maison-atelier Foujita. CD91. Fondation Foujita. ADAGP2019
家のところどころには、藤田が絵を描いたらしい皿や、屏風などがある。さすが画家の家と思いきや、その物自体を彼が作ったのだという。
あまり知られていないことだが、創作家としての藤田の才能は絵画だけでなく、数々の工芸や手仕事にも向けられていた。パリに最初に来た頃から、貧しさもあって裁縫は自分で手がけ、衣装やカーテンを作り、さらにブリキ細工、木工、陶芸、家の模型づくりなどまで、作れるものは何でも試した。特に裁縫はプロ並みで、若い頃ロンドンにいた時には仕立服のブランド「セルフリッジズ」で雇われてもいたという。
この家には、彼のこうした「創造」への尽きない興味と、暮らしの道具へのこだわりがあふれていて、しかもそのすべてに「藤田らしさ」が感じられる。美術館では知ることのできない、もう一人の藤田嗣治の姿を見る思いがする。

藤田が手がけたテーブルクロスやナプキン ©Maison-atelier Foujita. CD91. Fondation Foujita. ADAGP2019
ダイニングスペースの片隅におかれたテーブルのクロスやナプキンは、まさに彼のお手製。下のクロスは風呂敷を使って作られていて、端には丁寧に「FOUJITA PARIS」と手で書いた布が目印に貼りつけてある。

©Maison-atelier Foujita. CD91. Fondation Foujita. ADAGP2019
藤田が自分で描き、焼いた陶器も数多く残されている。この一風変わった「猫の聖母子像」の皿は50年代に藤田が作り、ヴァロリスという南仏の街にあるピカソも愛用した陶器の工房で焼いたもの。下の写真に映った2枚も藤田の手によるものだが、右上の皿に描かれているのは「狂乱の時代」を象徴するフレンチカンカンの「足」で、彼が絵画にもよく描いていたモチーフだ。

©Maison-atelier Foujita. CD91. Fondation Foujita. ADAGP2019
先ほど見た流しの壁には、伝統的な絵柄のタイル。デルフト焼きや彼がメキシコ旅行で手に入れたというタイルも張ってあるが、よく見るとその大半は、実は普通の白いタイルに藤田自身が貼ったデルフト模様をプリントしたシールだ。
職人顔負けのお手製調度品や日用品をたくさん自分で造った彼だったが、ここだけは急ごしらえだったのかもしれないと思うと、ちょっと微笑ましい。

©Maison-atelier Foujita. CD91. Fondation Foujita. ADAGP2019
上階にはリビングと寝室が一体になった広い居室空間がある。庭へと大きく開けた窓が印象的な間にはイタリアの家具デザイナー、マルコ・ザヌーゾによる当時は珍しかったソファベッド。ここに座ると見える暖炉には、これも藤田が描いた「綱引きをする子どもたち」のかわいらしい絵が描かれている。もちろん「綱引き」はフランスの文化にはない。その様子を、絵を見せながら友人たちに説明する藤田の笑顔が思い浮かぶようだ。

綱引きの様子が描かれた暖炉 ©Maison-atelier Foujita. CD91. Fondation Foujita. ADAGP2019
彼の創作と試行錯誤がつまったアトリエ。
そしてクライマックスは、やはりこの家の最上階にあるアトリエ部分だ。絵を展示した美術館が表舞台だとすれば、ここは画家・藤田嗣治がその数々の作品を生みだした舞台裏であり、魂を注ぎ込んだ実験場と言ってもいいだろう。藤田はここで一日10〜12時間も籠もり、あの特別な乳白を生み出した彼がずっとそうしてきたように色の調合や筆運びやモチーフの研究を重ねていたという。

最上階のアトリエ ©Maison-atelier Foujita. CD91. Fondation Foujita. ADAGP2019
作業台、イーゼル、画布、額、数え切れないほどの筆、彼がさまざまな創作をするための工具や素材、裁縫用のミシンまで、あらゆる彼の遺品がそのまま残されている。
そしてなにより圧巻なのは、天井まで届きそうな壁画だ。私たちがよく知る藤田の絵画と少しトーンが違うこの絵は、彼がランスに建てた礼拝堂の内部に描いたフレスコ画の習作。つまり練習用の下書きである。フレスコ画は、ヨーロッパの多くの教会に見られるが、「fresco(新鮮)」が意味する通り、漆喰を壁に塗ったらそれが生乾きのうちに石灰水に溶かした顔料で絵を描かねばならない。その方法がゆえに後世に保存可能な作品になるのだが、一方で油絵のようなやり直しはきかない。

©Maison-atelier Foujita. CD91. Fondation Foujita. ADAGP2019
それまで一度もフレスコ画を手がけたことのなかった藤田は、その方法をマスターするためにここで練習を重ねたのだった。デッサンをし、モチーフを確認し、漆喰を塗り一気に描き上げる。その繰り返しの生々しい痕跡は、見る人の心を震わせる。
この大作に挑む自分を、数々の教会絵画を手がけた敬愛するイタリア絵画の巨匠に重ね合わせたのだろうか。アトリエには、藤田が描いたレオナルド・ダ・ヴィンチやミケランジェロのポートレートも残されている。
彼は人生最後の大仕事となった礼拝堂の建設と壁画の制作を、当初この村でと考えていたという。しかし村には予算がなく、結果、彼の友人であり、洗礼の代父を務めたシャンパーニュのメーカーG.H.マムの社長ルネ・ラルーが資金と土地を提供。藤田は自分をフランスという国にあらためて迎えてくれたシャンパーヌの都への深い敬意を込めて、それをランスに造ることを決意したのだった。
80歳になる年に、彼はランスで礼拝堂のフレスコ画に着手。内部全体を包むような壁画を、アトリエと同じように毎日12時間もかけて取り組み、驚くことにたった3ヶ月で描き上げた。礼拝堂が完成したのは1966年10月。彼が滞在先のスイス・チューリッヒで亡くなるわずか1年3ヶ月前だった。
彼を看取った君代夫人は、この家の作品や遺品を散逸させることなく守り続け、1991年にエソンヌ県にそのまま寄贈。2000年、夫妻の願い通り一般に公開された。いまも県の遺産として、大切に受け継がれている。
フランスには美術家が残したアトリエや住居が公開されていることが少なくないが、デッサンや画材、生活の道具に至るこれほどの遺品が保存されているケースは極めて希と言っていいだろう。それがゆえに、私たちは藤田嗣治の人となりを、全霊を込めて理想を追った作家の魂を、そして夫人と共に過ごした生活に注がれた愛情を、肌身で感じることができる。
藤田嗣治そのもののような家を、後世の私たちが見ることのできる幸せ。これからもずっと永く残されていくことを心から願わずにはいられない。

Maison-atelier Foujita
メゾン・アトリエ・フジタ(藤田嗣治の住居兼アトリエ)
7, route de Gif à Villiers-le-Bâcle
91190 France
<ガイド付き見学> 無料
開館日:土曜14 :00〜17:00/日曜 10 :00〜12 :30 および14:00〜17:30
平日は要予約で5名以上のグループのみ

©Maison-atelier Foujita. CD91. Fondation Foujita. ADAGP2019 Scénographie de Frédéric BEAUCLAIR
住居兼アトリエのとなりにある建物には、藤田嗣治の生涯を数々の作品や遺品、写真とともに辿る展示室。現在、日本人陶芸家・桐谷純子さんの作品が展示されている。
杉浦岳史/ライター、アートオーガナイザー
コピーライターとして広告界で携わりながら新境地を求めて渡仏。パリでアートマネジメント、美術史を学ぶ高等専門学校IESA現代アート部門を修了。ギャラリーでの勤務経験を経て、2013年より Art Bridge Paris – Tokyo を主宰。現在は広告、アートの分野におけるライター、キュレーター、コーディネーター、日仏通訳として幅広く活動。