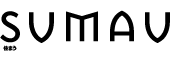パリとアート
心の「目」で見たままを描く強さ。
パリ「ナイーブ・アート」展。

Senlis, Photo © Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais /Jacqueline Hyde
「ナイーヴ・アート」という言葉をご存じだろうか。
「ナイーヴ」といっても「繊細で傷つきやすい心」の意味ではない。そのように使われるのは日本くらいで、語源になった英語の「naive」、フランス語の「naïve / naïf」は、もともと「素朴な」「自然な」という意味だ。美術史の中で「ナイーヴ・アート=素朴派」といえば、19世紀から20世紀にかけて、とくに美術の教育を受けずに「素のままに」絵画を描き、特殊な才能を開花させた画家たちのことをいう。

André Bauchant / Les Baigneuses, vers 1923, Huile sur toile, 102,5 x 133 cm, Collection particulière ©Adagp, Paris, 2019
パリ7区、日本人にもよく知られる百貨店「ル・ボン・マルシェ」に近いマイヨール美術館では展覧会『税関吏ルソーからセラフィーヌまで ~ 素朴派の巨匠たち』が始まり、2020年1月19日までつづく。「素朴派」と名づけられてはいるが美術界ではいわゆるアウトサイダーであり、こうして展覧会としてまとめて紹介されるのはとても貴重な機会となる。
フランス人を中心に展示される本展の中での注目は、女流画家セラフィーヌ・ルイの作品だ。

Séraphine Louis / Les Grappes de raisin, vers 1930, huile sur toile, 146 x 114 cm, Collection particulière, Photo : © Jean-Louis Losi
その名を聞いて思い出すのは、2009年フランス映画界のアカデミー賞ともいわれる「セザール」賞で作品賞、主演女優賞をはじめ7つの部門を受賞した映画『セラフィーヌの庭』。この作品は日本でも話題になった。
この映画の主人公が、セラフィーヌ・ルイ。彼女は1864年にパリ近郊の町に生まれた画家だった。「画家」といっても美術の教育は一切受けたことがなく、むしろ極めて貧しい農村の生活の中で、家畜の世話や住み込みの家政婦をしながらその日暮らしをしていた。
彼女は夜になると、昼に摘んであった花や草、仕事場でくすねた動物の血や教会の蝋・精油などあらゆる身近な素材から絵の具をつくって絵を描く。彼女がつつましい仕事で稼いだお金で買う唯一の高価なものは「白い絵の具」。自然の素材では作れないからだ。

Séraphine Louis / Feuilles diaprées sur fond bleu, 1929, Huile sur toile, 55 x 46 cm, Collection particulière
「守護天使のお告げ」を受けて40歳すぎから始めたという絵は、彼女の暮らしからは想像もつかないエネルギッシュな花や木や果物。使用人としてつらい目にもあってきた彼女は、自然の中で植物などに話しかけていたというが、他人には感じない何かをそこに見ていたのかもしれない。
その絵を、たまたま彼女が家政婦を務める屋敷に間借りしたドイツ人美術批評家であり画商のウィルヘルム・ウーデが発見。誰にも真似の出来ないような彼女の作風に圧倒される。

Séraphine Louis / Bouquet de mimosas, 1925, Huile sur toile, 147,5 x 98 cm, Laval, musée d’Art naïfs et des Arts singuliers, Cliché Ville de Laval
彼はすぐにセラフィーヌの作品を買い、彼女は欲しかった画材やキャンバスを手に入れ絵を続ける。しかし第一次世界大戦が始まり、敵国ドイツ人のウーデはフランスを離れることに。彼女は貧しい家政婦の生活に戻る。
終戦後、二人は再会。貧困から抜け出せていないセラフィーヌはそれでも絵を上達させていた。ウーデはパリでアンリ・ルソーなどと共に彼女を展示。すぐにコレクターがつき、セラフィーヌは一瞬の「理想的な画家」の時間を経験するが、今度は「世界恐慌」の波が彼らを襲う。真っ先にアートが売れなくなってウーデも財政基盤を失い、彼女への支援をやめてしまう。失意の中で彼女は心を患い、絵を描くこともやめ、第二次世界大戦中に精神病院で亡くなってしまうのだった。
「素朴派」の作家たちは、このセラフィーヌ・ルイのように、自らの情熱や信念の趣くままに絵を描いた。教官もいないから、過去の画家や技術にとらわれることなく、先入観もなく、ただ夢想家としての無尽蔵な想像の力で、執拗なまでに作品に向かいつづける。だからこそ、時に誰の思いも寄らない、常識を越えた素晴らしい作品が生まれるのだ。
同じ時期に、やはりウィルヘルム・ウーデによって見いだされたカミーユ・ボンボワもその「素朴派」の一人だ。

Camille Bombois / Fillette à la poupée, 1925, Huile sur toile, 55 x 46,5 cm, Collection particulière, Photo : © Jean-Louis Losi © Adagp, Paris, 2019
カミーユ・ボンボワは、南仏のある町で水上の物売りの息子として生まれた。腕っぷしの強さからサーカスのレスラーになり、同時に絵を描き始めたという変わった経歴を持つ。憧れだったパリに出てきて地下鉄の工事や印刷工の仕事などもこなしながら、残った時間を使って絵を描き続けたという。
徴兵された第一次世界大戦の戦場で功績を挙げて帰還すると、彼の絵は詩人のノエル・ビューローの目に留まり、パリのモンマルトルで展示される。やがて雑誌に載るなどするうちに、ウィリアム・ウーデなど画商にも扱われるようになり、42歳を過ぎてようやく画家として生活できるようになるのだった。

Camille Bombois/ Portrait de femme (Madame Meyer-Mekler), 1928, Huile sur toile, 41,3 X 33 cm, Collection particulière © Adagp, Paris, 2019
彼の絵にはサーカス時代や子供の頃の水辺の情景が多く描かれる。ふくよかな女性がモデルになった絵も多く、そこには同じ時代の画家の誰とも違う、人に対する豊かな情感や、生のエネルギーのような力強さが感じられる。人物のボリュームや構図は時に不自然だが妙にバランスがとれ、画面全体を引き締める「黒」の使い方も独特だ。

Camille Bombois / La Grosse Fermière sur son échelle, 1935, Huile sur toile, 100 x 81 cm, Courtesy galerie Dina Vierny, Paris © Adagp, Paris, 2019
他にも展覧会は「素朴派」のまさに巨匠といえる税関吏のアンリ・ルソー、園芸家のかたわら独学で絵を描き、最後は建築家のル・コルビュジエなどに見いだされたアンドレ・ボーシャン、郵便職員のルイ・ヴィヴァンなど、この当時偶然に「発掘」され、結果的に歴史に名を残した画家たちを一堂に紹介する。

Henri Rousseau dit le Douanier Rousseau / Deux Lions à l’affût dans la jungle, 1909-1910, Huile sur toile, 84,5 x 119,8 cm, Collection particulière. Photo : Archives de l’Hôtel des Ventes de Monte-Carlo

Dominique Peyronnet /La Forêt, Non daté, Huile sur toile, 61 x 81 cm, Nice, Musée International d’art naïf Anatole Jakovsky – Ville de Nice © Ville de Nice
19世紀の終わり頃から20世紀前半といえば、それまでの伝統的な絵画の世界が解体され、その描き方もモチーフもすべてが大きく変化していた時だった。古い画壇に対抗して、あえて変わったもの、突飛なものを求めていた時代だったということも、こうした素朴派の輝く原石のような作家たちが注目された理由でもあるのだろう。
ただそれ以上に、私たちはこうした素朴派の絵に心を揺り動かされる何かを感じる。感情のほとばしりを映した色彩。見たまま、感じたまま、想像したままを、ひたすらキャンバスに落とし込んでいったイメージ・・・。そこにあるのは過去の美術の歴史や他人の意見などといったものに左右されない、作家の純粋な「目」で見た世界観が持つパワーだ。発掘したのがドイツ人のウーデや、英米の画商などパリにおける「外国人」であることも見逃せない。同じ国の「異色」は往々にして軽蔑され、その新しさに気づけないというのはよくある話だ。
「コンセプト」が全盛となり、意味を問う作品に重きがおかれる現代のアートシーン。時には、原始の人間が洞窟の壁に描いたような「素のまま」のアートに目を向けてみるのもいいかも知れない。

René Rimbert / Le Douanier Rousseau montant vers la gloire et entrant dans la postérité, 1926, Huile sur toile,
100 x 56 cm, Collection Pierre et Margaret Guénégan © Droits réservés
『税関吏ルソーからセラフィーヌまで ~ 素朴派の巨匠たち』
2019年9月11日〜2020年1月19日
10:30〜18:30(金は20:30まで)期間中無休
マイヨール美術館(フランス・パリ)
61 rue de Grenelle, 75007 Paris, France
ウェブサイト www.museemaillol.com
杉浦岳史/ライター、アートオーガナイザー
コピーライターとして広告界で携わりながら新境地を求めて渡仏。パリでアートマネジメント、美術史を学ぶ高等専門学校IESA現代アート部門を修了。ギャラリーでの勤務経験を経て、2013年より Art Bridge Paris – Tokyo を主宰。現在は広告、アートの分野におけるライター、キュレーター、コーディネーター、日仏通訳として幅広く活動。