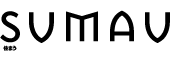パリとアート
近現代美術の宝庫、ポンピドゥー・センター。それは長い「美術の物語」が辿りついた場所。

なぜアートが人々を惹きつけるのか。美しいから?古くて価値があって有名だから?それだけだろうか。日本でも公開された2011年の仏映画『最強のふたり』で、アート愛好家でもある富豪の主人公フィリップは、「それはアートが、地球上で我々が残してきた唯一の足跡だからだよ」と言う。そう、まさにそれは人類の歴史そのもの。美しさを探究したいとか、恐れとか、愛とか、神を信じる心とか、あるいはパトロンの言われるがままになど、作品を作る動機はさまざまだったろう。いずれにしても、芸術家が熱意をもって制作し、それに心動かされた人々によって時には戦争をも乗り越えて大切に受け継がれてきた、その物語の積み重ねが「美術史」だといえる。
パリには、この人類の足跡を流れで見ることができる国立の美術館が3つある。ルーブル、オルセー、そしてポンピドゥー・センター。この3つはおおむね受け持つ時代が決まっている。古代から1800年代前半まではルーブル美術館。欧州を革命の嵐が吹き荒れた1848年から後期印象派あたりまでを扱うオルセー美術館。そして1900年代以降の作品を、ここポンピドゥー・センター近代美術館が担う。
パリ市庁舎にも近い、まさに街のど真ん中にある建物は、建築家のレンゾ・ピアノとリチャード・ロジャースを中心にしたチームの設計によるもの。周辺の建物との調和という概念からかけ離れたかのような配管むきだしの姿は、1977年の完成当初には当然のように賛否両論があがったという。それから40年。人々の目は慣れてきているはずだが、それでも今なお斬新さと違和感を放ち続けているというのは、ある意味、称賛に値する。

建物の中に入るまでは無料。広い1階は、インフォメーション、ミュージアムショップ、チケット売場などがある。ここでチケットを手に入れて透明なチューブの中のエスカレーターで上階の展示場へと向かう。


上層階からはパリの絶景も楽しみたい。
1900年以降といえば、特にフランスでは印象派後の美術界でクラシックな様式や画壇のしがらみからアーティストが解き放たれて、思いのまま、探究心のおもむくままに「新しい芸術、自分の芸術とは何か」を追求。アートが壮大な実験場になりはじめた時代。最初はフォーヴ(野獣)派と呼ばれる、現実とは違う色彩の洪水からはじまって、ピカソやブラックのキュビズムへ。やがては未来派、ダダイズム、抽象主義、あるいはそれまでの時代にはあり得なかった素材を使うなどして、数限りない様式へと多様化していく。ここポンピドゥー・センター近代美術館の5階から4階にいたる常設スペースは、20世紀のアートがあらゆる方向に拡散していった時代の流れが見てとれる場所だ。

アンリ・マティス Henri Matisse / Luxe, Calme et Volupté, 1904
この、さまざまなアーティストが想像力と創造力を駆使して作品を創ってきた過程が、フランス人たちには格好の話題を提供する。大人たちは作品を前に、まるでカフェにでもいるかのように美術談義。作家の考えがこみいってくるほど、それを想像する側でも、ああでもないこうでもないと話がひろがる。子どもがいれば、親はもっているだけの知識量とアドリブで説明、あるいは「これは何?なんでこれを作ったの?」と質問し、子どもたちは思ったままに答えを口にしていく。いまのアートに「正しい答え」はない。そこにはさまざまな作家のモノの見方やアイデアがたくさんつまっていて、それに気づくことで見る人は考え方の多様性を知ることができるのだ。

イヴ・クライン Yves Klein, ANT 76, Grande anthropophagie bleue, Hommage à Tennessee Williams,1960
現代社会が生みだす素材を芸術にしたセザールの回顧展。
こうした20世紀以降のアートの実験性と多様性を代表する作家の一人、フランスの美術家「CÉSAR セザール」(1921〜1998)の回顧展が、いまここポンピドゥー・センターで3月まで開催されている。

César / Fanny Fanny, 1990, Courtesy Foundation César, Bruxelles
彼は彫刻家として活動を開始。といっても、ブロンズや大理石ではなく、身近にあった金属の廃材や廃棄物が材料だった。最初はそれを組み合わせ溶接、人物や動物などの彫刻作品を創って人気を得ていたが、ある日、プレスされたスクラップカーに出逢って衝撃を受ける。1960年に3つの自動車を圧縮した「3トン」という名の作品をパリで発表して美術界にスキャンダルを巻き起こし、同時に彼の名は一躍世の中に知られるようになった。
その後も、親指や乳房の型をとってそのまま大きくした「拡大」シリーズ、発泡ポリウレタンのふくらみを最大限に活かした「膨張」シリーズなど、彼は近代の産業社会から生まれる素材を徹底的に実験し尽くし、その可能性に挑み続けた。それを大量消費社会への批判ととらえる人もいるし、単純に見た目がすごい、面白い、クールだと思う人もいるだろう。もしかしたら彼は絵の具や絵筆の代わりに廃材を駆使し、粘土をこねる代わりに機械でプレスし、ただただ無邪気にそこから生まれる造形のとりこになっていたのかもしれない。
常識に囚われない視点から生まれる、限りない創造のトライアル・・・。美術の世界に新しい地平を切り拓いた圧倒的な「塊」の作品群は、まだまだ私たちに訴えかける力をもっている。

César / Blu Francia 490, 1998, série “Compressions”

パリのアトリエで「膨張」シリーズを製作するセザール
César réalisant une Expansion, Atelier de la rue Lhomond, 1967, photo ©Michel Delluc
ポンピドゥー・センター 国立近代美術館
「セザール」回顧展
2018年3月26日(月)まで
https://www.centrepompidou.fr/en(英語版ウェブサイト)
杉浦岳史/ライター、アートオーガナイザー
コピーライターとして広告界で携わりながら新境地を求めて渡仏。パリでアートマネジメント、美術史を学ぶ高等専門学校IESA現代アート部門を修了。ギャラリーでの勤務経験を経て、2013年より Art Bridge Paris – Tokyo を主宰。現在は広告、アートの分野におけるライター、キュレーター、コーディネーター、日仏通訳として幅広く活動。