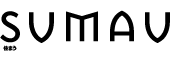パリとアート
「ナビ派」- 印象派とピカソの間で、
美術界の静かな革命を試みた男たちの話。

パリのサンジェルマン・デ・プレ地区の南には、リュクサンブール庭園という広大な緑地がある。面積は約22.4ヘクタール。東京でいえば日比谷公園の約1.4倍の広さがあり、綺麗な噴水や数々の彫刻、美しい花々が季節を彩り、ポニー広場やテニスコートまである。昼はカルチェ・ラタンの学生達や近隣のオフィスの人々がランチをしたり、家族がピクニックをしたり。夕方には仕事帰りに待ち合わせた恋人たちが愛を語りあい、ジョギングしたり、本を読んだり・・・いわば、パリの美しい日常がそこにある。

「公園」でなく「庭園」と呼ばれているのは、もともとが「リュクサンブール宮殿」の庭であったことによる。ここは最初、ルイ13世のお母さんにあたるマリー・ド・メディシスの居城として1615年に建設が開始された。その後は王家や貴族の要人が後を継ぎ、フランス革命後は牢獄になって、ルーブル美術館に所蔵されている有名な大作『ナポレオンの戴冠式』を描いた画家ジャック=ルイ・ダヴィッドが一時期投獄されていたりもした。宮殿の建物は今も庭園のシンボルとして北におかれ、現在はフランス国会のひとつ「元老院」が議事堂としてそれを受け継いでいる。

そのリュクサンブール宮殿の東棟に1750年に設立されたのが「リュクサンブール美術館」だ。実は美術館としての歴史は長く、ルーブル宮殿が美術館になったのより40年以上も早い。

いまこのリュクサンブール美術館で開催されているのが「ナビ派と装飾芸術」展だ。
「ナビ派」は「印象派」や「キュビスム」などのように近代美術のひとつの潮流。あまり聞き慣れない名前かも知れないが、19世紀から20世紀にかけての美術で重要な橋渡しをした活動として、近年あらためて注目を集めている。時期としては、印象派が注目された少しあと、ポスト印象派に位置づけられる画家のゴーギャンやゴッホなどが活動していた頃にあたる。
1888年、ポール・セリュジエという、のちに「ナビ派」の主人公のひとりとなる画家とこのゴーギャンが出会ったことで、新しい波が始まることになる。
パリのアカデミー・ジュリアンという絵画塾にいたポール・セリュジエは、この年の夏、フランス・ブルターニュ地方のポン・タヴェン村を訪れ、ここに集まっていた画家たちのリーダー的存在だったゴーギャンに会い、教えを請う。ゴーギャンは、他の画家たちも交えセリュジエを森に連れて行き、ある助言を与えたという。
「君にはこの木がどう見えるかね。黄色に見える?なら黄色をおきたまえ。影はどうだろう?むしろ青く見えるかね?ならば純粋なウルトラマリンを。そして葉が赤いならバーミリオン(赤)をおきなさい。」と。予定された色でなく、自分の心で感じたものを描くよう勧めたのだった。
当時は革命的とされた「印象派」でさえ、現実を忠実に再現するという意味においては写実的だった時代。パリに戻ったセリュジエが伝えた大胆な「ゴーギャンの教え」に、ピエール・ボナール、モーリス・ドニ、ポール・ランソンなど学生仲間たちはワクワクを止められなかった。エドゥアール・ヴュイヤールなど学外の友人らも交えて新しいグループを結成し、そこにヘブライ語の「預言者」を意味する「Nabis ナビ」という名前をつけ、新しい美の追求を始める。
「ナビ派」の始まりである。

Maurice Denis, Avril, 1892, huile sur toile, 38 x 61,3 cm / Otterlo, Kröller-Müller Museum © Otterlo, Kröller-Müller Museum
日本美術との出会い。
若いナビ派に影響を与えたのは、ゴーギャンの言葉だけではなかった。1890年の春にパリ国立美術学校で開催された「日本の版画展」。ここで「ナビ派」の作家たちが「浮世絵」にふれた。
すでに1867年、1878年のパリ万博を通じて「ジャポニズム」が開花し、印象派の芸術家たちに影響を与えていたが、若いナビ派の画家たちにはこれが初めての日本美術との出会いだった。浮世絵などにおける単純化された形象や鮮やかな色づかい、そしてなによりも空白を活かした大胆な構図、また遠近法を用いない平面的な日本美術のあり方は、それまでの西洋絵画の立体感を見慣れた彼らには衝撃的だったらしい。

vue de l’exposition Les Nabis et le décor (2) scénographie Hubert Le Gall, Laurie Cousseau © Rmn-Grand Palais / Photo Didier Plowy
ピエール・ボナールの作品『庭の女性たち』は、まさにこの日本美術の影響がみてとれる。4枚の絵の縦に長い構成は日本の掛け軸(フランスでは「kakemono」と呼ばれる)を思わせ、女性たちよりもむしろ水玉の模様や色、それと一体化するような背景の植物の装飾性が意識されている。

Pierre Bonnard, Femmes au jardin, Femme à la robe à pois blancs, 1891, peinture à la colle sur toile, panneau décoratif, 160,5 x 48 cm, Paris, musée d’Orsay © Rmn-Grand Palais (musée d’Orsay) / Hervé Lewandowski
絵画が「装飾的」であるというのは、この当時とても斬新なことだった。それまでは人物にしても、神話にしても、風景にしても、何が描かれているかという「主題」に重きをおいていた。しかし、ナビ派の画家たちは画面の中での線や色彩の構成が呼応しあい、それだけで調和を保っていなければならないという信念があったという。それはほぼ時を同じくして起きる「アール・ヌーヴォー」にも通じるものがある。

Maurice Denis, Arabesque poétique dit aussi L’Echelle dans le feuillage, 1892, huile sur toile montée sur panneau de bois, 235 x 172 cm / Saint-Germain-En-Laye, musée départemental Maurice Denis © Rmn – Grand Palais / Gérard Blot / Christian Jean

Paul Ranson, Trois femmes à la récolte, 1895, peinture à la colle sur toile, 35 x 195 cm / Saint-Germain-en-Laye, musée départemental Maurice Denis © D. Balloud
展覧会「ナビ派と装飾芸術」展は、この「装飾的」であったナビ派に注目する。実際に彼らは、芸術は誰もがそれを利用できるものであるようにと、タペストリーや壁紙のプロトタイプ、ステンドグラスや陶磁器の世界にまでそれを応用して、この分野に革新的な影響を与えた。

Maurice Denis, Les Colombes, vers 1893, projet de papier peint, aquarelle, crayon et gouache sur papier, 106 x 50,3 cm / collection particulière © catalogue raisonné Maurice Denis, photo Olivier Goulet
装飾とはいえ、それが今のような「デザイン」になるのではなく、彼らが関心を抱いていたモチーフと融合してあくまで絵画である点が興味深い。ナビ派が好んで描いたのは、まるで浮世絵がそうであったように何気ない日常のシーン。特に「アンティミスト(親密派)」と自らを称したピエール・ボナールとエデュアール・ヴュイヤールは、妻や家族、室内をひたすら描いた。一方で、目に見えるものではなく内面の世界を描くという延長上にある精神性、宗教など神秘的なものも題材になった。ポール・セリュジエの『水くみの女性たち』は、その象徴的な一枚だ。

Paul Sérusier, Femmes à la source, 1899, détrempe sur toile, 131 x 57,4 cm / Paris, musée d’Orsay © Musée d’Orsay, Dist. RMN-Grand Palais / Patrice Schmidt
このように、目に見えるものでなく内面の世界を描き、大きな物語でなくとても個人的な日常を描き、世紀末を背景にした神秘的な情景を描き・・・と、この時代の絵画のさまざまな流れを汲みながら、生活に芸術を採り入れる「装飾」として絵画を高めていったナビ派。それはまさに19世紀から20世紀へ移る、美術界激動の時代を象徴する活動だったといえそうだ。
描く対象から絵画を離していくという画家たちの試みは、このとき決定的なものになった。ここからさまざまな流れを経て、やがて絵画は抽象表現へと向かっていき、用の美であるデザインにも多彩な挑戦が始まる。もちろんこのあとの数々の紆余曲折をひと言でまとめられるはずもないが、ナビ派を通して美術史を捉えると、20世紀美術の物語も少しはわかりやすくなるかもしれない。
Les Nabis et Le Décor ナビ派と装飾芸術
2019年6月30日まで
リュクサンブール美術館
19 rue de Vaugirard, 75006 Paris, FRANCE
詳しくは公式ウェブサイト(英語)へ
https://en.museeduluxembourg.fr/
杉浦岳史/ライター、アートオーガナイザー
コピーライターとして広告界で携わりながら新境地を求めて渡仏。パリでアートマネジメント、美術史を学ぶ高等専門学校IESA現代アート部門を修了。ギャラリーでの勤務経験を経て、2013年より Art Bridge Paris – Tokyo を主宰。現在は広告、アートの分野におけるライター、キュレーター、コーディネーター、日仏通訳として幅広く活動。