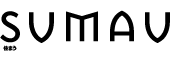パリとアート
忘れられた「後ろ姿」に光をあてる。
パリ、ブールデル美術館「BACK SIDE」展。

私たちはふだん、人のどこを見ているだろうか。さまざまな答えがあるだろうが、やはり視線は正面や顔に向けられがちで、後ろ姿はどうしても二の次になる。なにしろ私たちは、自分で直接背中を見ることさえできない。
しかし、ファッションの世界では前も後ろも同じように重要視される。創り手は「後ろ姿」を真剣に飾り立て、あるいは露わにし、強調する。絵画、写真、彫刻などの世界でも、背中、後ろ姿はその想像をかき立てるミステリアスさや、人の裏側や内面を見るような感覚で、常に創作のモチーフになってきた。
多様な表現を持ちながら、これまで光があたってこなかったこの「背中」に焦点をあてた展覧会『BACK SIDE / DOS A LA MODE モードの後ろ姿』が、パリのブールデル美術館で始まった。
最初にあえて強調しておきたいのだが、アートとモードを融合した展覧会で、これほど素晴らしいものは近年なかっただろう。企画の切り口、場と展示の構成、すべてが見事に調和している。2019年11月までと期間も長いので、パリ旅行の際にはぜひ訪れることをおすすめしたい。

ブールデル美術館エントランス
ブールデル美術館は、19世紀から20世紀にかけてパリのモダンアートが隆盛を極めた時代の聖地、モンパルナス地区にある。国鉄の一大ターミナルであるモンパルナス駅からも近く、今は近代的な建物が多く建っているが、当時は緑や葡萄畑などがあったところにアパルトマンが並びはじめたばかり。多くの画家や彫刻家が広いスペースを求めてアトリエを構え、夜は賑やかなカフェに集った。
そんな芸術家のひとり、彫刻家アントワーヌ・ブールデルのアトリエ・アパルトマン跡を中心に、彼の死後約20年経った1949年に開館したのがこの美術館だった。同じくパリのアトリエが美術館になったオーギュスト・ロダンやギュスターヴ・モローほど知られてはいないが、庭園とアトリエ、彼のアパルトマン、そしてあとから増築された展示室まで、そのシーンのひとつひとつが美しい。

今回の企画展では、パリにおけるモードの殿堂である「パレ・ガリエラ」服飾美術館のコレクションから、「後ろ姿」をテーマにした約100体の服、そして写真、映画が、このブールデル美術館を舞台に展開される。

グランドホール ©Pierre Antoine
最初に目にするのは、1961年に増築された「グランドホール」と呼ばれるブールデルの石膏原型像を中心にすえた展示室。彼の名を有名にした『弓を引くヘラクレス』(1909)をはじめとした巨大な像の中に、クレア・ワイト・ケラーによるジバンシィ2018春夏の作品、カール・ラガーフェルドが1983年に手がけたクロエのプレタポルテ秋冬の作品などがならぶ。どちらも背中を大胆に開けながら、エレガントなラインを描き上げる。

カール・ラガーフェルドによるクロエ1983-84秋冬の作品 ©Pierre Antoine

工房に飾られた川久保玲の作品 ©Pierre Antoine
中庭に向けた大きな開口部をもったブールデルの工房に飾られたのは、川久保玲によるコム・デ・ギャルソンの1997プレタポルテ春夏『Body Meets Dress』の作品。そのデフォルメされた背中や腰の形が、同じ室内に置かれたブールデルの名作『瀕死のケンタウロス』の首を不自然に傾けた造形とも呼応して、理想的な身体とは何かを私たちに問いかける。
そしてメイン展示室<ポルザンパルク翼>では、18世紀から現代まで、背中をどう見せるかに趣向を凝らした数々のスタイルが、モードの歴史とともに明らかになる。ところどころには、やはり背中の造形にこだわりを見せたブールデルの彫刻作品。ロダンの弟子でもあった彼の知られざる「身体表現」が垣間見えて興味深い。
最初に私たちを迎えるのは、2019年春夏プレタポルテ・コレクション79ブランドのショーで撮影され即座にネット配信された3524枚のショット。すべてが画一的な正面の写真で、後ろ姿は完全に忘れられている。

©Pierre Antoine
そして展覧会は数々ある「後ろ姿」の表現を、いくつかの類型に分けて紹介する。人の動きの軌跡を追うような「トレーン=引き裾」の表現は、その最も古典的なものかもしれない。13世紀の昔から、それは富と権力の象徴として発展し、今もウェディングドレスや夜会服に受け継がれる。身体の動きをしなやかに、エレガントに見せる基本の造形はおそらく永遠に残るのだろう。

Jean Paul Gaultier, « Arabesque », Trench coat dress, Haute couture, Fall-Winter 2011-12
© Françoise Cochennec / Galliera / Roger-Viollet
写真の世界でも、背中の魅力に取り憑かれた作家が多い。1933年、パリに生まれたフランスを代表する写真家ジャンルー・シーフもその一人だ。彼は1960年代から90年代にかけてモノクロームによる数々の「後ろ姿」を写真におさめ、1985年には展覧会「Back is beautiful」を開催。独自の「背中」観を創りあげた。

Jeanloup Sieff, Hilde in a dress too small, Paris, [Hervé Léger’s dress, published in Dépêche Mode
1995] © Estate of Jeanloup Sieff
背中には「背負う」という役割があるせいか、時にファッションでも積み荷のようなスタイルを持ち込まれることがある。2001年のヨウジ・ヤマモトのバッグ一体型ドレスはまだ優美さを残しているが、2016年にリック・オウウェンスが発表した人間リュックは、ショーの時には実際の人間を背負ったモデルがランウェイを歩き、モードファンの度肝を抜いた。

©Pierre Antoine

©Pierre Antoine
そして人の背中といえば、忘れられないのは古代から存在する「翼」のモチーフだろう。天使のように神性を帯びたり、軽やかさの表現だったり。翼そのものを使ってきた作品も多いが、2013年のコム・デ・ギャルソンは、その現代版といえるデザインだ。

Comme des Garçons, Suit Bermuda shorts, Ready-to-wear, Fall-Winter 2013-14
© Françoise Cochennec / Galliera / Roger-Viollet
西洋の衣服の歴史で、なぜか女性だけに課された不思議なスタイルがあった。それは「背中で締める服」だ。背中の上から下まで留めなくてはならず、よほど肩が柔らかくなければ自分では着られないものも多い。これは古い時代のそれを着けてくれる夫への依存を象徴しているともいわれるが、男性を魅了し、あるいはフロントを美しく見せるスタイルとして現代まで残ることになった。中には拘束着のようなもの、あるいは写真右にあるゴルチエ2003年秋冬の作品のように、頭の先から腰までを紐で結ぶややアブノーマルなものも現れて、特別な「後ろ姿」を生みだすことになる。

©Pierre Antoine
そしてやはり最も多く見られるのは「ヌード」、すなわち肌を露出するスタイルだろう。女性の身体は隠すものという伝統が続く中で、初めて背中を見せる服がモードの世界に現れたのは19世紀の終わり。せいぜいうなじと肩のちょっと下までを見せる程度だったという。それが第一次世界大戦が終わって海水浴が一般的になる頃に発展、また1930年代にハリウッドの映画界で胸元をはだけるのが禁止された代わりに、背中を大きく開けた服が好まれるようになったという逸話もある。以来、背中そのものをどう美しく見せるかにファッションデザイナーたちが工夫を凝らし、今やそれが一般化していることはご存じの通りだ。

©Pierre Antoine

©Pierre Antoine
ここまで見てくると、いかにモードの後ろ姿が雄弁に文化や社会のあり方、人間の心の動きを語ってきたかがわかる。そしてどれほど私たちが後ろ姿に無頓着であったかも。セルフィー全盛の時代、私たちの目はつい顔に向けられ、スマートフォンのカメラは勝手に人の顔を認識し、そこに焦点をあてようと試みる。けれど時には視点を変えて人間の背が何を語っているかをゆっくり見つめる時間があってもいいだろう。なにしろ、私たちの身体の半分は後ろ姿なのだから。
展覧会[BACK SIDE / DOS A LA MODE]
ブールデル美術館(パリ)
18 rue Antoine Bourdelle 75015 Paris
期間:2019年7月5日(金)〜11月17日(日)
開館時間:10:00〜18:00 (月休、祝日も休館日あり)
料金:10€(18歳以下および常設展示スペースの見学は無料)
ウェブサイトhttp://www.bourdelle.paris.fr/
杉浦岳史/ライター、アートオーガナイザー
コピーライターとして広告界で携わりながら新境地を求めて渡仏。パリでアートマネジメント、美術史を学ぶ高等専門学校IESA現代アート部門を修了。ギャラリーでの勤務経験を経て、2013年より Art Bridge Paris – Tokyo を主宰。現在は広告、アートの分野におけるライター、キュレーター、コーディネーター、日仏通訳として幅広く活動。