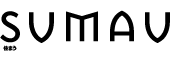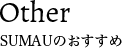The Food Crafter
緑と水と太陽の大地を
つむじ風のように豚が駆ける

名水100選に選ばれた菊池渓谷の清流と
田園風景の広がる熊本県菊池市へ
“走る豚”。そのキャッチーなネーミングを聞いたのは少し前のこと。
野山を駆け巡って育つ豚がいるらしい。まるでスペインのどんぐりを食べて育つイベリコ豚のようではないか。日本でそんな風景が見られるならば、ぜひ行ってみたいと思った。
走る豚がいるのは、熊本市の東北部に位置する菊池市。阿蘇外輪山の中腹にあたる菊池渓谷から清らかな水が潤沢に流れる、水のきれいな街として有名で、天皇家や将軍家に献上された米どころとして知られている。また古くから酪農の盛んな街でもある。この菊池市にあるやまあい村(農園)が目指す場所だ。

江戸時代から美味しい米の産地として知られる、菊池市七城は田園風景が広がる
やまあい村の看板を目印に車で山道を分けていると、代表の武藤勝典さんがニコニコと出迎えてくれた。走る豚のいる山の中まではかなりの道なき道を行くというので、いったん武藤さんのトラックの荷台に乗り換えて、まさに車一台がギリギリに通れる山道を登って行く。
日本では数少ない豚の放し飼いがやまあい村で始まったのは約19年前。武藤さんのお父さんの時代のことだ。そもそものきっかけは、農業を営む武藤さんの隣の土地が、産廃御者に売られるという話が出たことにあった。それでは困るというわけで、お父さんが山を買い取ったのだった。
「買ったはいいけど、何しろ山なので畑には向かないし、
使い道に困ってしまって(笑)。
それで、もともと養豚をやっていたこともあって豚を放してみたのが始まりです」

林の中に放された走る豚。涼しい木陰でのんびり過ごしている
山の中にはいくつかに分かれて豚の放牧地がある。林の中やだだっ広い原っぱなど、豚が下草などを食べつくすと場所を入れ替えながら移動する。走る豚は生まれた順に小グループで育つのだ。放牧される期間はおよそ7、8ヶ月。一般的な養豚では5、6か月で出荷されるので、やまあい村は少し長い。
「豚舎で育つ豚にくらべると走り回っているので、
どうしても大きくなるまでに時間がかかるんですよ」

武藤さんの愛情たっぷりに育つ豚たち。大好きなさつまいもをもらって大満足。
国内では珍しい放牧で
育てることに意味がある
ヨーロッパでは、豚は放牧で育つことが多いというが、日本では豚舎で飼うのが一般的だ。広い運動場で放し飼いにすることはほとんどないという。その理由は管理がしやすいことにある。もしかしたら、日本では土地が狭いことも一因なのかもしれない。
しかし、やまあい村の豚たちは広い大空の下、草原の草を食べ、泥んこになって転げ回り、仲間と遊びながらのびのびと育つ。そのせいか、穏やかで実にいい顔している。人懐っこくて好奇心も旺盛、人間を見かけると『何だ、何だ』と野次馬のように寄ってくる。
「豚は病気に弱い動物なので病気を持ち込まないように隔離して育てる方法もあります。
でもうちはその反対で、自然の中でたくましく育てることで、
自己免疫力が高まり、病気になりにくい健康な豚に育つと考えています」

緑の草地に放された豚たち。この牧草も食べている。
武藤さんの走る豚はやまあい村で生まれ、母豚のミルクを飲んで育つ。乳離れしたら山に放たれて、さつまいもや飼料、農家で取れた野菜を食べて、1日中気ままに過ごすのだ。豚にとってはストレスがなく、見ていてとても気持ちの良い方法だが、育てる側としては手間やコストがかかる。生産者の立場としては苦労も多いに違いない。
「農業は多面的な役割を担っている仕事です。
経済や食料はもちろん、環境、地域、文化、などなど……。
それが経済のみに引っ張られるとバランスを崩してしまう。
僕は人ややらない、機械ではできない、面倒くさいことを仕事にしようと思っているんです」
ストレスがなく育つことで
料理人が喜ぶ豚肉になる
走る豚は、料理人の間でも有名になりつつある。初期の頃はオーガニックショップなどを中心に卸していたが、最近ではレストランへ卸すことも増えてきた。農場へ見学に来る料理人も少なくないという。
走る豚にほれ込んだ料理人の一人が菊池にあるコントルノ食堂の菊池健一郎シェフだ。土地の食材使ったイタリア料理で、県外から食べにくる人も多い人気店だ。

走る豚の肩ロース。赤みが強く、程よく脂もある。コントルノ食堂ではこれで生ハムを仕込んでいる。
コントルの食堂では走る豚を一頭買いする。肩ロースは自家製の生ハムになるがこれが絶品。脂がきれいで肉も繊細で味わい深い。
「野生では、1日の大半をかけて豚は食料を探して動き回るので、
筋肉が発達して肉が固くなりますが、
食料がもらえる走る豚は、休息行動も多く、食べて遊んで寝ていることも多いんです。
だから走る豚の肉は、思ったよりも柔らかいんですよ」と武藤さんはいう。

完成から1年たった、コントルノ食堂の生ハム。脂が透き通って甘みを増している。
一頭買いした肉を余すところなく使い切るため、端肉などはサラミなどの加工品にしたり、煮込んだりして無駄なく全てを食べ尽くす。走る豚はほどよく運動しているので、肉が締まっていて赤身の味わいにも深みがある。これがプロのシェフの手にかかると、劇的に美味しくなることが分かってきたという。今では一頭買いで、プロの料理人に委ねられることが増えてきた。

山に囲まれた菊池市の美しい夕景。この街に武藤さんのやまあい村がある。
武藤さんにはこれから取り組みたいことがある。それが雄豚の肉の美味しさを追求することだ。一般的に、雄豚は臭いといわれて嫌がられるため、小さい頃に去勢される。仕事の中では去勢の仕事が一番きらいだという武藤さん。健康な体にメスを入れることに抵抗があるからだ。そこで、雄豚が去勢されることなく、健やかに育つ道を模索しているのだ。
「かつては、解体の時に睾丸などを傷つけてしまって
臭いが付くことがあったかもしれませんが、
今は解体の技術も進んでそんなことはなくなりました」
実は、実際に去勢しない雄豚を育てて検証してもらったこともある。東京の消費者団体やイタリアンのシェフを通して、お客さんの反応を見てもらったという。結果はとても良好で、雌豚とくらべても問題なく、むしろちょっとしたクセが返って味のアクセントになるという評価をもらった。
「近い将来、去勢されない雄豚を一般流通にのせたいと思っています」
最近では、アニマルウェルフェアという言葉も注目されている。
これは、感受性を持つ生き物としての家畜が、ストレスなく、健康的な生活ができる飼育方法をめざすという考え方だ。ますます畜産の在り方が問われるこれからの世界にあって、武藤さんのチャレンジはまだまだ続いていく。
やまあい村
(取材&文・岡本ジュン)