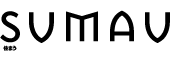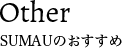アーティストインタビュー
日本でフレンチスタイルの花の美学を広める
ローラン・ボーニッシュさん


「秋色の素材」
ダリア、秋色のアジサイを中心に、バラの実、ウイキョウ、日本の秋を彩るヤマゴボウを組み合わせたアレンジメント。こんもりとまとめられたダリアとアジサイに、ウイキョウやバラの実の伸びやかな形状を活かして配置。
色や素材感、香りを大切にした
日本の花が好きだから日本で活動を続ける
――ローランさんの作品は、どれも繊細なのに、とても自由でのびのびとしているように感じます。
すべての作品で、自分自身が幸せを感じられるものだけを表現しています。好きな花を選んで、花を大事に扱い、花に愛を込めてブーケをつくっている。ルールや技術は大切ですが、特別なことをしているわけではありません。
わたしにとって花はとても身近な存在なんです。当たり前にあるもので、なくてはならないもので、愛しいと思わせてくれるもの。実家は曽祖父の代から続く花屋で、パリのブローニュの森に近い高級住宅街ヌイイ市というところで暮らしていました。
店にも家にも街にも、緑や花が溢れていました。花は幸せになるためのものだと思っているので、作品を見て驚いたり幸せな気分になってくれたりするなら、わたしもとてもうれしいですね。

「秋の田園風景」
アジサイで秋の穏やかな雰囲気を演出したブーケ。ヒペリカム、バラの実のほか、ペンペン草など野の草も豊富に取り入れることで、美しさのなかに奔放さと生命力も感じさせる仕上がりになっている。

来日15年を迎えアトリエを設立したローランさん。フラワーデザイナーとして、パリ流生活芸術という概念で暮らしの美学を日本で広めている。
――パリで16歳から24歳までフラワーデザイナーとして活動し、来日して15年が経ちました。日本とフランスのちがいを感じることはありますか?
四季があるのはパリも日本も同じですし、いまの時代、たいていの花はパリでも日本でも手に入ります。ヨーロッパと日本で大きくちがうのは、生産者の環境です。
ヨーロッパには個人の生産者は多くはありません。たとえばバラはエクアドルやケニアの大規模農園で生産されたものがヨーロッパ全土に流通しています。
一方、日本では個人の生産者が意欲を持って花を生産している。試行錯誤を重ねながら新しい品種を生み出す方も多く、日本の生産者しかつくってない花に真っ先に出会うことができます。
日本の花農家の方は、色や素材感、香りをとても大切にしているし、品種の個性を引き出しながら花を育てるのがうまいと思います。
いわば、よくできた大量生産の家具ではなく、職人が丹精込めて仕上げた一点ものに近い感覚。私がいまも日本で活動を続けている理由のひとつは、そういう日本の花が好きだからです。

「アンティーク・カラー」
バルボティーヌと呼ばれるアンティークの器に、ローランさんが名づけたバラ「ジャルダン・パフュメ」をはじめオールドローズ系の素材を入れたアレンジメント。バラ、ミント、ヒペリカム、唐辛子などを使い、大人っぽい色の組み合わせでシックに仕上げている。

ローランさんが名前をつけた品種「ジャルダン・パフュメ」が美しいアレンジメント。フランス語で「香りの庭」の意味で、香りが高く静岡県三島の市川バラ園が生み出した。

「日本の花農家の方は、色や素材感、香りをとても大切にしていて、品種の個性を引き出しながら花を育てるのがうまいと思います」とローランさん。