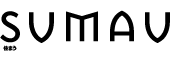フランスの美しい村
フランス、西の最果てで伝統を受け継ぐ、
ビグダン地方の刺繍祭り。

ヨーロッパには多くの民族衣装がある。日本人になじみがあるのは英国スコットランドのキルト、あるいはドイツのチロリアン、チェコ、ブルガリアなど東欧のかわいらしい衣装などだろうか。フランスで「民族衣装」といってもあまりピンと来ないかもしれないが、一部にはそれを守りつづけている地域がある。
そのひとつ、ブルターニュ地方に色彩やその細かな技巧で知られた民族衣装の大規模なパレードが行われる町があると聞いて訪れた。
パリから超特急TGVに乗って約3時間半。フランス西端に近い都市「カンペール」から、さらにバスで30分ほど揺られていくと、そこに「Pont L’abbé ポン=ラベ」という人口8000人ほどの小さな町がある。

ポン=ラベは干潟が川のように内陸に入り込んだ珍しい地形の町。潮が満ちるとここは港になる。

地元の人々がポン=ラベ川と呼ぶ干潟沿いは自然豊かな絶好の散歩路。

かつてポン=ラベ城であった建物はビグダン博物館、そして町役場として使われている。
ブルターニュ地方は、ヨーロッパの原住民であったケルト人の末裔、ブルトン人が住むことでその名前が生まれた。荒々しい海に囲まれた厳しい気候もあいまって、フランスの一部に組み込まれながらも独立心が強く、今も地域によってはフランス語とはルーツの異なるブルトン語という言葉を生活の中に残している。

聖ジャック・ド・ランブール教会跡・1675年「赤帽の反抗」事件で壊され、以後修復されることはなかった
訪れた町「ポン=ラベ」はブルターニュ地方の「フィニステール県」に属するが、ポン=ラベの人々はそれよりも古くからの民族としての伝統や精神性といったアイデンティティを表現する「Bigouden ビグダン」という地域名を誇りをもって語る。そこはブルターニュ地方の中でもさらに独特の文化を根づかせてきた場所。特に衣装に関しては、もともと自分たちの文化にこだわりを持つこの地方の風土に加え、町どうし、あるいは他の地域とのライバル意識もあって、独自のスタイルで発展を遂げてきた。

ここで年1回、7月第2週に開催される「刺繍祭り」は、その文化を今に伝えるフェスティバル。1909年から続くという「刺繍の女王コンテスト」を発展させる形で1954年から始まり、今年で66回目を迎える長い歴史があるお祭りだ。
期間中は、ポン=ラベをふくむ「ビグダン」地域、ブルターニュ地方の各地を中心に、それぞれご当地の民族衣装を身につけた約50ものグループがやってくる。子供からお年寄りまで、多くの人が自前の衣装を着て町を練り歩き、列になって民族舞踊を披露したり、ブリテン島つまり今の英国やアイルランド方面からやってきたブルトン人のルーツを思わせる、バグパイプなどの楽隊の音楽も町に響きわたる。


期間中の土曜日には、子供たちだけのパレードも。ふわりとしたスカートやフランス語で「タブリエ」と呼ばれるエプロン、頭につける頭巾「コワフ」は女の子たちがつけるとまるで人形のよう。300人以上のかわいらしい子供たちが、1年に1度の舞台を晴れやかに、真剣に、時に恥ずかしそうに歩いていくさまが、集まった観衆を笑顔にしてくれる。



そして日曜日の朝は、このフェスティバルのメインイベントとなる大人たちのパレード。「刺繍祭り」の本領発揮ともいえる各地から集まった1000を超える種類のコスチュームが目の前を通りすぎていく。美しい女性達の姿が多いが、結婚したカップルや最近生まれた子供とその家族、あるいはこの衣装がまだ生活の中で現役だった時代を知っているお年寄りの参加もある。すべての参加者に共通しているのは、その民族衣装を着ていることへの喜びと誇りが感じられることだ。

特に注目したいのは、まるでコック帽のように背の高いコワフ。そして男女の上着の胸などに施されたオレンジや黄色や青の緻密な刺繍だ。これらはまさしくここ「ビグダン」の地に特徴的なスタイルなのだが、このコワフの高さや刺繍の色や模様が、同じ地域の中でも町・村によって違っていて、競いあいながら個性を高めていった歴史があるという。「ビグダン」地域の面積は日本でいえば東京23区より少し小さいくらい。たとえるなら、その区ごとに違う民族衣装があって、ひとめ見ただけでどの区かわかるようなものだ。

コワフの高さも、こうした強い郷土愛と競争心から生まれたもの。昔はカトリックの宗教上の理由からフランスの他の地方と同じように髪を隠す頭巾のようなものだったのが、第1次世界大戦後の1918年頃から高くなりはじめ、第2次世界大戦前の1940年頃までに最大で高さ38cmまで達したという。それに合わせて刺繍やリボン、レースもどんどん緻密で装飾的になった。

コワフの高さが少しずつ高くなっていった歴史の変遷が見られる展示スペース
さらに不思議なのは、これが祭礼のためだけではなく、日常のものだったということだ。女性たちは朝起きると髪を整え土台を作ってコワフを被り、日中をずっとこの姿で過ごしたという。大戦後、時間をかけてその習慣は失われていくのだが、1992年の時点でもその生活を送っていた女性が643人いた。今では93歳のアレクシアおばあちゃんがたった一人の生き残りだ。

今年93歳になるアレクシアさん(中央)と記念撮影をする若い女性たち
刺繍もかつては「ビグダン」の人々の日常的な稼業。ブルトンの衣装独特の分厚い生地に刺していく刺繍は力仕事で、この地方では多くの男性がこれに従事していた。今は職業として刺繍を手がける人はもういない。

緻密な刺繍が施されたアンティークのベストを着る彼は、民族衣装のコレクターでもある。
お祭りの盛大さの一方で、少しずつ失われていく文化だが、それを新しいカタチで未来へつなげていこうという動きも現れている。
一時は有数の刺繍産業拠点だったポン=ラベで最後の刺繍工房であった「LE MINOR ル・ミノール」。廃業寸前だったこの老舗を、地元出身、美術史家でロシア・エルミタージュ美術館の展覧会キュレーションも手がけたティエリー・モレル氏が引き継いだ。彼はビグダンの伝統的な刺繍を残しながら、有数のアーティストとのコラボレーションなどにより新しい刺繍の可能性を探る。

LE MINOR を受け継いだティエリー・モレルさん

刺繍製品や工芸品で郷土の文化を見せるLE MINORの店内。上階に刺繍アトリエがある。
生活様式や考え方が大きく変わった現代社会で、古くからの文化を残すことは容易ではない。郷土の文化やそれへの愛着が根強く残るここビグダン地域でさえ残念ながら例外ではなかった。けれども、若い世代が積極的にお祭りに参加し、町のDNAを受け継ごうとする人々がいる以上、形を変えてもそれは伝えられ、また新しい文化が生まれていくのだろう。ビグダンの民族としての誇りが後世に残されていくのか、もしかしたら今この時代が正念場なのかもしれない。

取材・文/杉浦岳史