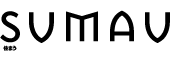パリで輝く女性たち
「和凧」にかける人々の想いを写す。
日仏二人の女性のプロジェクト。

日本のお正月の風物詩のひとつ、大空を舞う凧(たこ)。
しかし読者の皆さんの中で、最近この凧を実際に見たことのある人がどれだけいるだろうか。都市で凧揚げのできる場所は減る一方で、20世紀のはじめに数百あった和凧製作の工房は、今や15軒ほど。そして、その中の多くは継承者がいない。今でも年賀状に多く描かれる伝統的な和凧は、実は過去のものになりかねない状況にある。
その和凧の魅力に惹きつけられるように日本に来たフランス人女性セシル・ラリさん。そしてパリで活躍する写真家・清真美(きよしまみ)さん。ふたりの女性が、今回のストーリーの主人公だ。

日本文化研究家のセシル・ラリさんと写真家の清真美さん(パリ Passage Jouffroy)
事の始まりは、ラリさんの日本文化研究。彼女はパリ・ソルボンヌ大学の博士課程で日本の写真史について研究をしていたが、その中で研究対象になった3人の写真家が、皆なぜか和凧や郷土玩具を被写体に選んでいたり、滞在先の外国で凧を揚げて楽しんだ経験を語ったりしていたのだった。その偶然の一致に彼女は何かを感じ、同時にフランスでは見たことのなかった色鮮やかな玩具との出会いに虜になった。
世界共通の言語である写真よりも、日本の郷土玩具、とりわけ和凧のほうが日本の文化の本質に近づけるのではないか・・・。「写真」よりは「日本」を研究したかったラリさん。世界中の民族文化に関する膨大な所蔵品を持つパリの国立ケ・ブランリー美術館で調べると、こけし、箱車、そして和凧などたくさんの所蔵品が出てきた。そして和凧が単なる玩具ではなく、平面に描かれた「絵」であり、ひとつの芸術として地方色も豊かに広がる、いわば日本文化を代表するような存在だということを知った。
「私の代で終わりでしょうね」の言葉に触発されて。

柳瀬重三郎さん(静岡県掛川市横須賀のやなせ提灯店にて)100年以上前に大祖父の柳瀬重太さんが創業。遠州横須賀の凧の11の定型種類はこの店でほとんど生みだされた。もともとは提灯工房で凧づくりも請け負う。©清真美
和凧について一歩進んだ研究をしたいとケ・ブランリー美術館に提案し認められると、2014年に日本の地をふたたび踏んだ。東京・日本橋の「凧の博物館」や大凧祭りで知られる東近江の「世界凧博物館」、そして全国に散らばる製作者や収集家に出会った。
最初はケ・ブランリー美術館にある42の和凧について資料、製作者、年月、描かれたモチーフを明らかにする調査が目的だった。しかし、1年をかけて調べ、話を聞くうちに、ある思いが芽生えていた。もう跡継ぎのいない年老いた製作者は、口々に「私の代で終わりでしょうね」と言う。そうなると今何とかしなければ、伝統はなくなってしまうかもしれない。実際、凧祭りなどで守られている地域以外では、凧づくりや遊び方を子どもたちに教えられる親がもはやいない。継承者がいる間に話を聞き、研究をまとめ、日本と世界の人々に伝えたいと、ある心に秘めたプロジェクトの実現に向けて動きだした。
ちょうどケ・ブランリー美術館に研究を持ちかけていた頃、あるパリの展覧会で出会った日本の女性写真家がいた。清真美さん。一目見て、ラリさんはその独特の世界観に引きこまれた。
和凧を愛する人々の情熱を写真に残す。

落合家(2005年、茨城)©清真美
それは『新釈肖像写真』と名づけられた清さんのライフワークともいえるポートレートシリーズだった。家や職場など、被写体にとって大切な場所に行き、一日をかけて直接話を聞き、そのストーリーをもとに、彼らの持っている品々を使って、まるで舞台のように写真のシーンを設定する。目指しているのは人生をぎゅっと閉じ込めた神話のような物語とその主人公である被写体の姿。そこから「一生でたった一枚のポートレート」が生まれる。
2010年、文化庁の新進芸術家海外研修制度のアーティストに選出され、東京からパリにやってきた清さん。2003年から始めた『新釈肖像写真』はすでに約60作品を数えていたが、そこから今度は人種や文化の違う人々を被写体にするという、このシリーズを始めて以来の想いをかなえようとしていた。

Bramble rose, Idril, Zinger (Paris, France, 2014 ) ©清真美
ラリさんは、和凧を現代の生きた文化として伝えるためには、文章だけでなく、ビジュアルでその鮮やかさと共に伝えるべきだと感じていた。和凧の製作者や愛する人々、収集家などの姿を清真美さんの作品と自分の研究で表現していきたい・・・。そこから、ふたりのコラボレーションが始まった。
実はラリさんは、清さんの作品に一目で関心を持ち、出会ってすぐに自らモデルにもなった。だからこそ、その作品づくりが表面的なイメージの撮影ではなく、モデルへの聞き取りを通じて、その内面に入り込み、映しだすものであることを身をもって体験していた。

Cecile (Paris, France, 2013) 清真美さんが製作したセシル・ラリさんのポートレート。祖国であるフランスとこよなく愛するアジアの2つの文化を両側に、画家であり研究者である本人が中央に立つ。 ©清真美
「和凧の美しさはもちろんですが、そこに関わる人の想いや情熱こそが大事だと感じていたんです。清真美さんの作品は、まさにその目的にかなうものだった。だからどうしても彼女に撮ってもらう必要がありました」

茂出木雅章さん(凧の博物館館長)と伊地知英信さん(日本の凧の会会報編集人)(東京都中央区たいめいけん・凧の博物館にて)茂出木さんはオムライスで有名なたいめいけんのシェフ。先代で背景の凧に映るたいめいけん初代の心護さんは博物館創設者で、今はこの2人がその遺産の保護者である。©清真美
2015年、ラリさんの丁寧な提案が実を結び、助成金の認定を受け、国際日本文化研究センターに所属してプロジェクトが始動した。ただ、その実現のための準備は簡単なものではなかった。
まず、凧の世界は多くが男のコミュニティだ。外国人の女性がそこに入り込むのは容易なことではない。製作者や全国の祭り、関係者のもとへ幾度となく足を運び、彼女の存在に慣れてもらい、そこに溶け込んでいくプロセスが必要だった。さらに撮影に協力してもらう、というハードルもある。中には堅気な職人肌の人もいれば、内気な人もいる。1日目にその人の物語を知るためのインタビュー、そして2日目に現場を設営して撮影するという、長時間の制約を受け入れてくれるかどうか。

石川昇さん(静岡県掛川市横須賀の凧のガレージの前にて)40年間アマチュアとして遠州横須賀凧11の定型を独学で製作してきた情熱家。手にしているのは自身で作った高さ4mの巴と呼ばれる凧。©清真美
「意外に大変だったのはやりとりで、凧の世界ではメールを使う人が少ないんです(笑)。予算とスケジュールの都合上、取材と撮影にかけられる期間は1ヶ月。郵便や電話で連絡しながら予定を決め、全国を巡るというのは難儀でした」
しかし地方の特色がほんとうに豊かな和凧の世界。できるだけ多くの「生きた証人」を得ることはどうしても欠かせないことだった。

撮影中の清さん。凧工房にあるさまざまなオブジェから、その人を表現する大切なオブジェを丁寧に並べて撮影の演出をする(撮影:遠藤裕己さん)
100年、200年後の人が、今の時代の営みを想像できるように。
怒濤のような1ヶ月の全国行脚を経て、ふたりのプロジェクトによる13点の新しい「新釈肖像写真」が完成した。
清さんは、これを「和凧の話」というタイトルで、「新釈肖像写真」シリーズの中のひとつの作品群としてまとめることにした。製作者、収集家ひとりひとりの物語から、和凧の大きな物語が立ちあがってくると思ったからだ。

伊藤さん家の凧工房(静岡県浜松市天神町)家族経営の凧製作工房。写真の中のヨコテンの凧のほか、浜松まつりの凧合戦に参加する173町のうち12の町の凧も作る。©清真美
清真美さんは言う。「今回、被写体となる人たちは、良くも悪くも凧に人生を大きく左右され、決定されている人ばかり。凧が人生と切り離せないものになっているんです。それだけに情熱も半端なく、内容の濃い作品づくりでした」
「日本の凧の地方ごとの特色とか、どう凧が受け継いでこられたのか、どんな気持ちで凧を作ったり、遊んだり、祭りが保存されてきたのか・・・。凧に関わる人のこの13枚のポートレートによって、日本の凧の大きな歴史や世界観が見えてくる。そんな作品群になったと思います。」

木村薫さん(大阪府池田の自宅にて)大阪の凧コレクターであり研究者。3,000点以上のオブジェや印刷物を収集、大部分を数年前に大阪歴史博物館に寄贈し、最も気に入ったものだけを手元に残した。特にコツマ凧と呼ばれる立体の凧では第一人者。©清真美
『新釈肖像写真』について清さんは、100年、200年後の人たちがこれを見たときにどう思うか、ということをいつも考えているという。彼女が好きなのは14世紀のフランドル画家の肖像画。それを見る私たちが当時の生活をさまざまに想像するように、今の時代の人間の営みを、作品から「読んで」ほしい、と。
この13枚のポートレートは、まさに和凧という文化とそれに関わる人たちの思いを次の世代に伝える貴重な存在になるに違いない。

小浦雄次さん(長崎県長崎市星取町の工房にて)小浦さんはセミプロの製作者で2009年に自分の手でこの工房を創った。ハタと呼ばれる長崎の凧は非常にグラフィック。ビードロと呼ばれる特別な揚げ糸は、相手の揚げ糸を切るためにガラス粉末で覆われる。©清真美
プロジェクトはまだ終わらない。昨年京都での展示会、パリでのシンポジウムが終わり、現在はパリで展示会を開催中。そして、清さんの作品とセシルさんの研究をもとに記事や書籍の刊行を目指し、日本はもちろん、世界にもこの独特の文化を伝えていきたいという。
私たち日本人でさえ、失われかけていることに気づいていない「和凧」の世界に光をあてた二人の女性のプロジェクト。その文化を情熱をもって守ろうとしている人々がまだ現役でいる今が正念場だ。

遠藤裕己さん(新潟県新潟市白根の自宅にて)大凧合戦で知られる白根のアマチュア製作者。日本の凧について国内や海外でも説明する機会が多く、そのための垂れ幕なども写真に見える。左の大きな六角凧の絵柄は彼によって描かれた。©清真美
清真美ウェブサイト http://www.kiyoshimami.com/
取材・文/杉浦岳史